現代社会では、人々が日々触れる情報量がかつてないほど増加しています。スマートフォンやタブレットを手に、SNSやニュースサイト、動画配信サービスを行き来しながら情報を受け取り、時には自ら情報を発信することが、多くの人にとって日常となりました。こうした「情報過多」の時代に注目されるようになったのが、「アテンション・エコノミー(関心経済)」という概念です。これは、情報の質そのものよりも、人々の関心や注目を集めることが経済的利益を生むという考え方を示したものです。
しかし、SNSの普及によってアテンション・エコノミーの負の側面が顕在化しており、深刻な問題となっています。注目を集めることを目的とした誤情報やデマ、いわゆる「フェイクニュース」がSNS上で急速に拡散され、それが人々の認知や行動に悪影響を及ぼす事例が増えているのです。
本稿では、アテンション・エコノミーの基本概念を整理し、その問題点を掘り下げます。特にSNS上で拡散されるフェイクニュースの深刻さ、その背後にある要因、そして私たちがこの問題にどのように向き合うべきかについて考察します。
1.アテンション・エコノミーとは何か

「アテンション・エコノミー(関心経済)」という考え方は、ノーベル経済学賞を受賞したハーバート・サイモンが提唱したもので、「情報が増えれば増えるほど、人が使える注意力が足りなくなる」という指摘から生まれました。サイモンは、情報が多すぎると、私たちが集中できる時間やエネルギーには限りがあるため、「関心・注目 (attention)」がとても大切な資源になると考えました。インターネットの普及で、今ではさまざまな情報が世界中で瞬時に流れるようになり、人々の注意を奪い合う競争がますます激しくなっています。
従来の経済学では、消費者が「お金を払って商品やサービスを得る」ことを中心に考えられてきましたが、アテンション・エコノミーの視点では「消費者にいかに自社のコンテンツに時間と関心を費やさせるか」が価値を生む鍵になります。つまり、人々の視線やクリック数、滞在時間など、「関心・注目」という無形資産を獲得することで広告収入やサービス利用料金などを得るビジネスモデルが成り立っているのです。SNSや動画配信サイトの運営企業は、ユーザーができるだけ長く自社のプラットフォームに滞在し続けるように、さまざまな仕組みを設計しています。
1-1.SNS普及とアテンション・エコノミー
近年ではSNSの普及がさらにアテンション・エコノミーを加速させました。SNSを運営する企業にとって、ユーザーがSNSで過ごす時間の長さはビジネス上の大きな指標です。ユーザーが長く滞在すればするほど、その間に表示される広告も多くなり、広告単価も上昇します。その結果、SNSはユーザーの関心を引き続けるために、エンターテイメント性や話題性の強いコンテンツを優先的に表示したり、閲覧履歴や「いいね!」などを分析してユーザーが「興味をもちそうな投稿」や「さらに見たくなるような投稿」をアルゴリズムによって積極的にレコメンドするようになりました。
こうした設計は多くの場合、ユーザーの利便性を高めたり、興味関心に合ったコンテンツを提示したりするなどのメリットをもたらします。しかし一方で、特定の価値観や情報だけを過度に強化したり、必要以上にセンセーショナルなコンテンツが拡散されることにもつながりやすく、これが「情報の偏り」や「誤情報の拡散」「フェイクニュースの蔓延」を招く温床にもなっています。
2. アテンション・エコノミーがもたらす負の側面
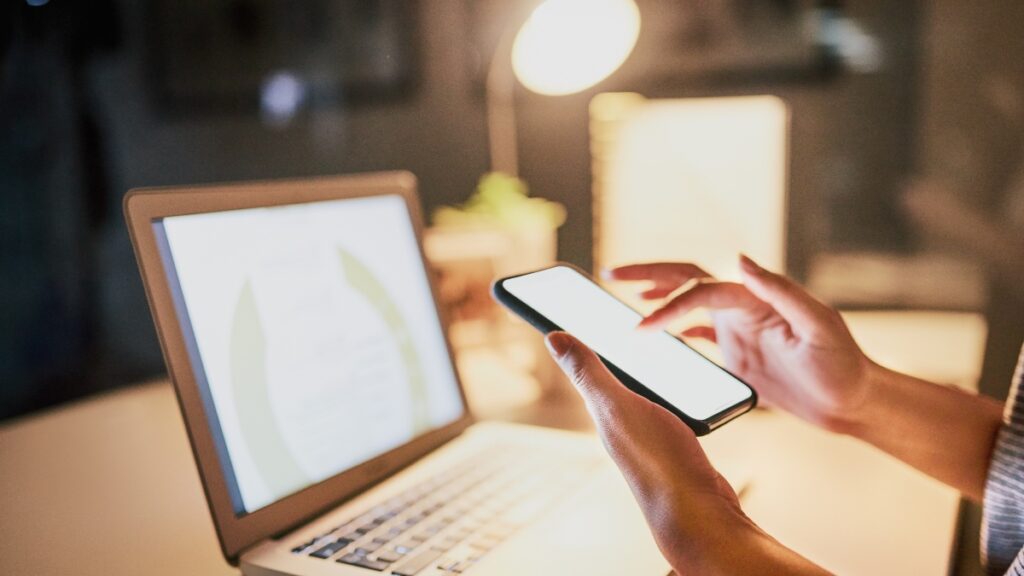
アテンション・エコノミーが持つ負の側面について、詳しく見ていきましょう。
2-1. 情報の過剰供給によるストレスと分散
アテンション・エコノミーが社会に浸透するにつれ、人々は常にあらゆる情報源からの刺激を受けるようになりました。SNSのタイムラインは途切れることなく更新され、動画ストリーミングサイトには膨大なコンテンツが並び、ニュースサイトやブログは次々と新しい記事を投稿してきます。こうした状況は、多くの情報から重要なものを選別して効率よく処理しなければいけないという心理的なプレッシャーを生むのです。
さらに、常にSNSをチェックしていないと「自分だけが重要な情報を見逃しているのではないか」というFOMO(Fear Of Missing Out:取り残されることへの恐怖)が生じ、ユーザーはより頻繁にSNSを覗きに行くようになります。こうして情報への欲求がかえって高まり、興味を引く刺激的なニュースや投稿に飛びつきやすくなるのです。しかし、その刺激的な情報が真偽不確かなフェイクニュースだったとしても、いったん目についたら流れてきた情報を「拡散」するのはほんの数クリックで可能なため、感情的な共感や批判とともにSNS上を瞬く間に駆け巡るという現象が頻発します。
2-2. 集中力の低下と思考の断片化
アテンション・エコノミーのもとでは、数多の情報が競争的に流れているため、人々は短い時間で多くのコンテンツを消費する傾向が強まります。その結果、ひとつのテーマを深掘りすることが難しくなり、断片的な知識が増える一方で総合的な理解や批判的思考が十分に養われない、という懸念が指摘されています。
SNSの投稿は短文が基本であり、文章を途中まで読んで結論を飛ばしてしまったり、タイトルのみで内容を誤解したまま拡散してしまうケースが後を絶ちません。また、ニュースサイトでも「見出し」がセンセーショナルな文言だったり、「クリックベイト」と呼ばれる過激なタイトルが使われたりすることで、実際の内容よりも大げさに解釈されることが多々あります。このように、短時間で多数の情報に触れようとするあまり、内容を深く吟味する前に「自分に都合の良い情報」や「感情を動かす情報」を安易に選び取り、そのまま周囲に発信してしまいやすいのです。
2-3. ポジティブフィードバック・ループによる偏りの増幅
SNSのアルゴリズムは、ユーザーの過去の閲覧履歴や「いいね!」の傾向などから、「このユーザーはこういうコンテンツに興味がある」と推定し、それに合致する情報を優先的に表示します。これは利用者の満足度向上に寄与する部分もありますが、同時に「自分の興味や信念に合った情報だけをどんどん強化するフィードバック・ループ」を生み出します。いわゆる「エコーチャンバー現象」とも呼ばれるこの状態では、同質の意見を持つ人々の間でのみ情報がやり取りされるため、異なる観点や反証などに触れる機会が減少し、特定の認識が過度に固定化されやすくなります。
極端な例としては、陰謀論や特定の宗教的・政治的主張がSNS上で一部のコミュニティ内だけで循環し、外部からの検証や批判を受け付けなくなることがあります。これは人々の分断を深刻化させ、社会全体で事実関係を共有し、公平な判断をすることを困難にする要因として問題視されています。
3. フェイクニュース拡散とアテンション・エコノミーの関係

フェイクニュースの拡散とアテンション・エコノミーとの関係について、詳しく掘り下げていきましょう。
3-1. フェイクニュースとは
フェイクニュースという言葉は、日本でも近年広く知られるようになりましたが、その意味するところは単に「誤った情報」だけではありません。多くの場合、フェイクニュースは「誤った情報を意図的に流布する」もしくは「誤解を招くように作為的に編集された情報」を指します。誤報やデマなども含みますが、意図的に人々を惑わしたり、感情を煽ったりすることを目的とするケースが問題の核になっています。
SNSの台頭以前にも、デマや陰謀論などの誤情報はコミュニティのなかでさまざまに拡散されてきました。しかし、SNS時代においてはその拡散速度と到達範囲が比較にならないほど広がったため、個人がもつ影響力が格段に増大し、結果的に社会全体が混乱するリスクが高まっています。
3-2. フェイクニュースが拡散しやすい要因
SNSを中心としたアテンション・エコノミーのなかで、フェイクニュースが拡散しやすい要因としては以下のようなものが挙げられます。
(1)センセーショナルな内容
フェイクニュースは往々にして刺激的な見出しや内容を伴うことが多く、閲覧者の興味を大きく惹きつけます。閲覧した人々がショックや怒りなどの強い感情を抱くと、SNS上で「このニュース、ひどい!」「驚いた!」などとコメントしながら拡散する傾向が強まります。
(2)アルゴリズムの偏り
ユーザーが一度、特定のフェイクニュースに反応すると、類似したコンテンツが優先的に表示されるケースがあります。ユーザーはさらにそれを拡散し、その投稿を見た別のユーザーも反応するという連鎖が起こりやすくなります。
(3)事実確認の困難さ
SNS上で流れてくる情報は膨大であり、受け手自身が一つひとつの情報の信憑性を細かく検証するのはほぼ不可能に近い状況です。また、「誰が書いたか」「どんな意図で書かれたか」がわからないままシェアされる投稿も多く、情報源の特定が難しいことも拡散の後押しをしてしまいます。
(4)バイアスの存在
人々はもともと、自分の考えや世界観を支持するような情報を信じやすく、反対意見や異なる事実は軽視する傾向があります(確証バイアス)。これにより、フェイクニュースであっても、自分の意見を強化するものであれば簡単に受け入れられやすいのです。
3-3. フェイクニュースの影響
フェイクニュースが拡散することにより、社会や政治、経済において深刻な影響が生じる可能性があります。例えば、選挙の時期に特定の候補者や政党を誹謗中傷する目的で作られたフェイクニュースが広がると、有権者の投票行動に直接的な影響を与え、公正な民主主義プロセスを歪めることになります。また、新型ウイルスや災害などに関する誤情報が広まれば、人々の混乱や不要な買い占め、差別や偏見を助長する結果となります。
さらに、こうしたフェイクニュースの蔓延によってメディア全体への不信感が高まり、「何が本当か分からない」「どの情報も嘘かもしれない」という懐疑的な態度が社会に蔓延すると、公的機関や科学的知見に対する信頼が損なわれ、社会システムそのものの機能不全を引き起こしかねません。
4. フェイクニュース拡散防止に向けた取り組みと課題

フェイクニュースの拡散を防ぐためにはどのような対策があるのか、また、どのような課題が存在するのかを見ていきましょう。
4-1. SNSプラットフォーム側の対策
フェイクニュースの拡散を防止するために、SNSプラットフォームを運営する企業はさまざまな取り組みを行っています。例えば、投稿の信憑性を第三者機関にチェックさせて「ファクトチェック済み」ラベルを表示する、誤情報と判断された投稿の表示範囲を制限する、不適切なアカウントの凍結や削除を行うといった対策です。さらにアルゴリズムの透明性を高める努力も一部で進められています。
しかし、これらの取り組みには限界があります。たとえば、フェイクニュースは投稿された直後の初動段階で爆発的に拡散されるケースも多く、プラットフォーム側がチェック体制を敷くころには既に大きく広まってしまっている場合があります。また、ファクトチェック機関やAIによる検知システムにも誤差や時間的遅れが生じることがあり、すべてを完璧にブロックするのは極めて困難です。
4-2. ユーザー側の情報リテラシー向上
フェイクニュース拡散を抑制するには、ユーザーが情報を受け取る際に「これは本当だろうか?」「情報源は信頼できるだろうか?」と批判的思考を働かせ、自律的に判断する力を養うことが不可欠です。具体的には、以下のような情報リテラシーを高める教育・啓発活動が求められます。
📌複数の情報源を参照する習慣
一つのニュースだけを盲信せず、他のメディアや研究機関、信頼できる個人などの情報と照らし合わせる姿勢を持つ。
📌タイトルや見出しだけで拡散しない
短い文章に凝縮されている情報ほどセンセーショナルな表現である可能性が高く、記事全文や出典などを確認したうえで拡散するか判断する。
📌デマや誤情報を見抜く基本的手法を学ぶ
画像や映像の加工の見分け方、URLやドメインなどから情報源を推測する方法、権威ある機関のデータや専門家の意見に当たるなどの手段を身につける。
ただし、このような情報リテラシー教育は学校教育や社会人教育の中で本格的に導入していく必要があります。大人であってもSNS上の誤情報に引きずられることは珍しくないため、幅広い世代を対象に継続的な教育が求められるでしょう。
4-3. 法的規制・ガイドラインの整備
一部の国や地域では、フェイクニュース拡散に対する法的な取り締まりや罰則を強化する動きも見られます。しかし、表現の自由との兼ね合いはデリケートな問題であり、規制が厳しすぎれば政府による言論統制につながるリスクも否定できません。フェイクニュースを悪用する個人や組織を摘発しつつ、健全な言論を委縮させないためには、慎重なバランスが必要になります。
各国の法制度やSNS企業の自律的なガイドラインのもと、フェイクニュースを明確に定義し、違反したアカウントを迅速に処分する仕組みを整備することが求められています。同時に、誤って事実に基づく情報まで削除したり、善意の投稿者に対する不当な検閲が行われないよう、透明性と公平性を担保することが重要です。
5. 我々はアテンション・エコノミーとどう向き合うべきか
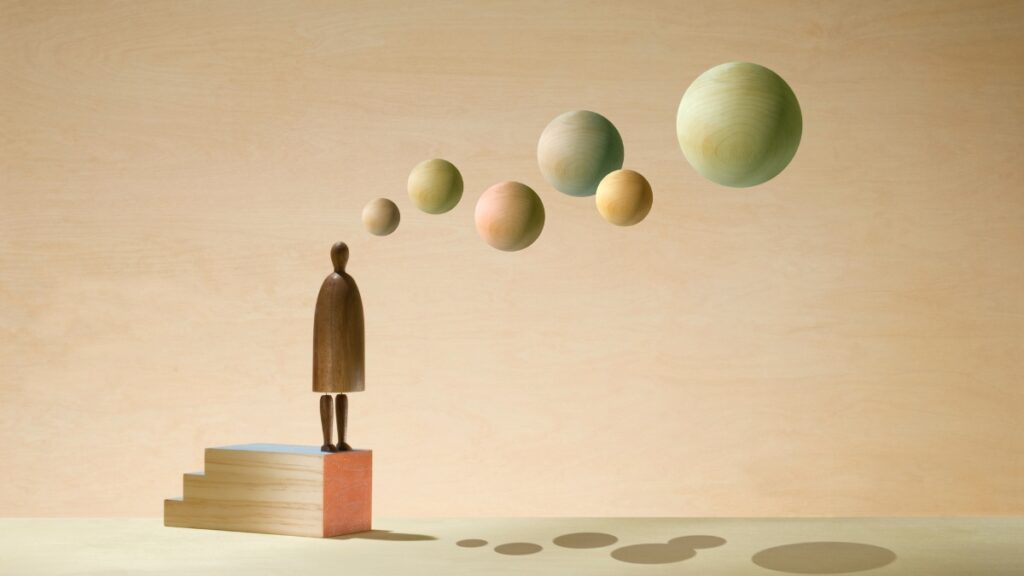
最後に、私たちがどのように向き合うべきか、そのポイントを解説します。
5-1. 自分の「関心」という資源を意識する
アテンション・エコノミーの世界では、ユーザーの関心がそのまま経済的価値に転換されます。そのため、多くの企業や情報発信者がユーザーの「関心」を奪おうと戦略を練っています。こうした状況を理解したうえで、「自分の関心は貴重な資源であり、むやみに消費されないようコントロールする」という意識を持つことが大切です。
具体的には、SNSをチェックする頻度や時間をある程度コントロールし、情報の海に溺れないように注意する、あるいは通知設定を見直して必要なものだけ受け取るなど、小さな工夫から始められます。もし必要以上にSNSを眺めてしまうことで情報のストレスを感じているなら、定期的にデジタルデトックスを試みるのも効果的でしょう。
5-2. 「情報を選択する力」を養う
膨大な情報がありふれる時代においては、「どんな情報を選び取り、どんな情報を捨てるか」を意識的に判断する力が求められます。SNSを利用する際にも、すべての投稿やニュースに目を通すのではなく、自分にとって本当に必要な情報は何かを常に問いかける癖をつけるとよいでしょう。
また、関心のあるトピックに関しては、信頼できる複数の情報源や専門家の意見にあたる習慣を身につけることも大切です。特に、社会的なインパクトが大きい政治や健康、経済に関するトピックでは、SNS上の偏った情報だけに依拠しないよう注意する必要があります。
5-3. 批判的思考と対話を重視する
アテンション・エコノミーがもたらす情報の断片化やエコーチャンバー現象に対抗するには、自分の持つ情報や意見が本当に正しいのかを常に検証する姿勢が欠かせません。自分と異なる立場の人々との対話を避けず、むしろ積極的に情報を交換して互いの認識を比較・検討することが、偏りや誤情報への対抗策となります。
オンライン上のコミュニケーションはしばしば対立や炎上を引き起こしがちですが、丁寧に情報を共有し合い、事実やデータを確認しながら議論することで、思わぬ気づきや理解を得られる可能性があります。対話の場を見つけ出し、ただ「感情的にぶつかる」だけではなく、お互いの立場の背景や理由を紐解きながら建設的なやり取りを目指すことが重要です。
6. まとめ
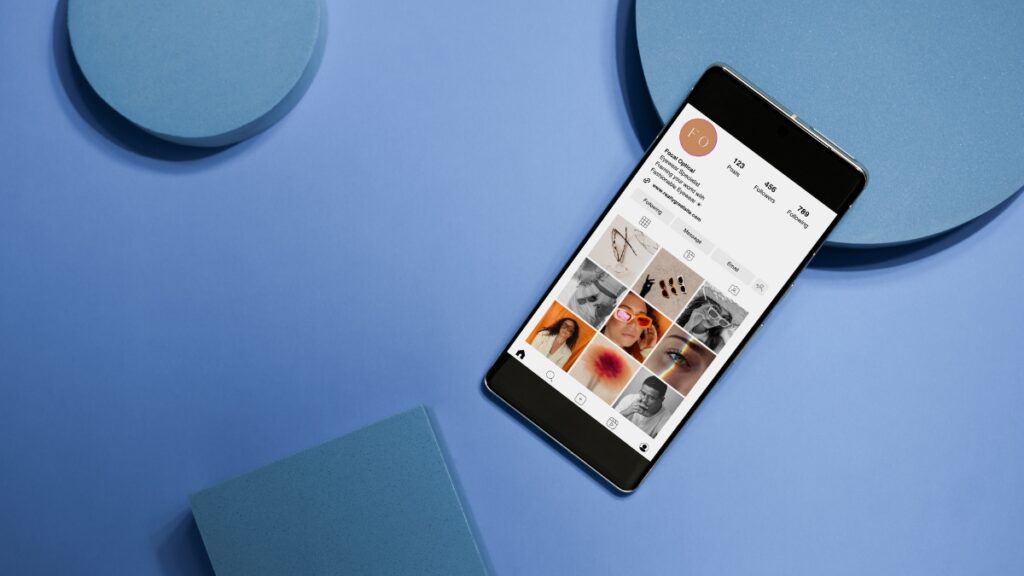
アテンション・エコノミーとは、人々の限られた「関心」という資源を巡って企業や情報発信者が競争し、その結果として膨大なコンテンツがあふれ返る現象を指します。SNSはこの仕組みの最前線に立つ存在であり、ユーザーがより長く留まるように設計されたアルゴリズムによって、興味や関心を引くコンテンツが次々と提示されるようになりました。これは利用者にとって便利で楽しい側面もある一方で、センセーショナルな情報が優先されやすい構造を生み出し、結果としてフェイクニュースや誤情報が拡散しやすい土壌を育んでいます。
フェイクニュースの広がりは、個人の認知や判断に影響を与えるだけでなく、社会や政治、経済に深刻な混乱をもたらす可能性を秘めています。誤情報を批判的に検証することの大切さは言うまでもなく、SNSプラットフォーム側の対策だけでは限界がある以上、最終的にはユーザー一人ひとりが情報を受け取る際の態度を変え、自分の「関心」をコントロールし、情報リテラシーを高めることが不可欠です。また、社会全体としてフェイクニュースや誤情報に対抗する法的・制度的な仕組みを整えつつ、表現の自由や健全な言論空間を維持するための慎重な調整が求められています。
アテンション・エコノミーの時代だからこそ、一瞬の刺激的な情報に惑わされることなく、複数の情報源を参照して事実を多角的に捉える視点が重要です。SNSをはじめとするネット空間と適切な距離を保ちながら、互いの対話を丁寧に行うことで、多種多様な情報にアクセスできる利点を活かしつつ、誤情報の蔓延を防ぎ、より健全で豊かな情報社会を築いていくことが期待されます。私たちは今後も、情報化社会の変化を見据えながら、自分自身の「注意」という貴重な資源をいかに活用し、また守っていくかを常に問い続ける必要があるのです。
※参考文献
*アテンション・エコノミー(attention economy)とは | NIKKEI COMPASS - 日本経済新聞

