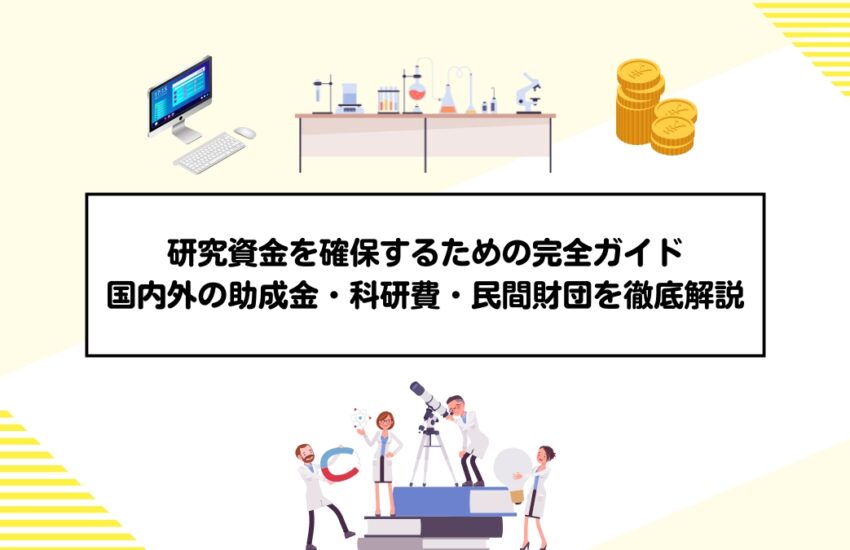研究を行うにはお金が必要です。たとえば、実験に使う試薬や装置、調査のための旅費、人件費、データ解析の費用、学会への参加費など、さまざまな場面で資金が求められます。
特に、大学や研究所で働く研究者は、給料は出ますが研究そのものに必要な道具やスタッフを雇う費用などは、自分で助成金(研究費)を獲得することが求められる場合が多いです。若手研究者の場合、まだ研究の実績が少ないため、お金を得るのは難しいと感じるかもしれません。しかし、国内外にはたくさんの資金源があり、それぞれに応募要件や特徴があります。
本記事では、研究者が資金を得る代表的な方法や、そのための工夫、申請時のポイントなどを、研究分野を問わず、なるべく分かりやすく紹介します。これから研究の世界に足を踏み入れようとする人や、既に研究しているけれど資金獲得で悩む人の参考になれば幸いです。
資金源にはどんなものがある?

1-1. 国や公的機関からの助成金
研究者がまず思い浮かべるのは、国の機関や公的な団体が提供する助成金です。日本の場合、「科研費(科学研究費助成事業)」と呼ばれる制度が有名です。これは文部科学省と日本学術振興会(JSPS)が運営しており、人文科学・社会科学・理工学・生命科学など幅広い分野が対象です。
科研費は多くの研究者が挑戦し、採択されれば研究費を使って自由に研究を進められます。ただし、申請書の審査は厳しく、研究計画がしっかりしているか、学術的な新しさがあるかなどが見られます。
ほかにも、科学技術振興機構(JST)や新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)などが特定の分野やテーマに特化した助成を行っています。これらは「競争的資金」と呼ばれ、応募者同士が競い合って採択される仕組みです。
1-2. 海外からの助成金
研究は国境を越えて行われます。欧州連合(EU)やアメリカの国立科学財団(NSF)、アジア圏の国際機関など、海外から資金を得るチャンスもあります。海外助成金に応募する際は、英語で申請書を書く必要があったり、海外の研究者とチームを組むこともあります。少しハードルは上がりますが、国際的な経験やネットワークを築くよい機会となります。
1-3. 企業との共同研究や受託研究
企業から資金をもらって研究する方法もあります。これは、研究成果が製品開発や技術革新につながる場合に特に有効です。大学や研究所が企業と契約し、研究者がそのテーマに沿った研究を行うことで、企業から研究費が支払われます。
このような「産学連携」は、基礎研究だけでなく応用研究、実用化へとつながる場合もあり、研究者にとっては資金だけでなく実社会への貢献を実感できるメリットもあります。
1-4. 民間の財団や公益団体からの助成
大企業が設立した財団、文化活動や環境保護、医療分野など特定テーマで支援を行う公益団体なども、研究助成プログラムを提供しています。国の助成よりは規模が小さいことが多いですが、その分ニッチな分野や独創的なアイデアに対して資金が付くこともあります。
特に若手研究者を応援する財団も多く、最初の一歩として小額の助成を得て実績を積み、次に大きな助成金に挑戦するといったステップを踏むことができます。
1-5. 寄付やクラウドファンディング
近年では、クラウドファンディングを使って一般の人から資金を募る研究者も増えています。「こういう面白いテーマを研究したい」という呼びかけに共感した人が少額ずつ寄付を行い、まとまった研究費が集まります。これは、研究を広く社会に知ってもらう機会にもなり、人々の関心や支持を得ながら研究を進める新しい資金確保の形です。
助成金を得るにはどんな準備が必要?

2-1. 明確な研究計画
助成金を得るには、まず「この研究は何を目的にしていて、どう進め、どんな成果が得られるのか」という計画が明確でなければなりません。申請書には、研究の背景、解明したい疑問、どうやって解決するのか、期待される成果や社会への貢献などを、分かりやすくまとめます。
2-2. 資金源ごとの特徴を理解する
助成プログラムごとに、対象分野、募集条件、支援期間、資金額などが異なります。たとえば、「若手研究者限定」とか「環境問題に関する研究のみ」など、条件があることもよくあります。自分の研究内容やキャリアに合った助成金を選ぶことが大事です。
2-3. これまでの研究実績やネットワーク
研究者としての実績(発表した論文、これまでの研究成果)は、審査で重要視されることが多いです。また、指導教授や共同研究者とのチームワーク、すでに業界で活躍する人脈もアピールポイントになります。助成金申請の前に同僚や先輩研究者に相談し、申請書をレビューしてもらうと、より良い計画書が作れます。
2-4. スケジュール管理
助成金申請には締切があります。申請書を書く時間、所属機関での手続き、共同研究者との相談など、やるべきことはたくさんあります。余裕を持って準備しないと、締切間際に慌ててミスをしてしまいかねません。計画的なスケジュール管理が成功への近道です。
日本で代表的な資金源と特徴

以下に、それぞれの資金提供団体の概要を解説します。
日本学術振興会(JSPS)
日本学術振興会(学振)は、研究者に対して研究費を提供する主要な資金源の一つです。特に、科学研究費助成事業(科研費)を通じて、人文科学、社会科学、自然科学など幅広い分野の学術研究を支援しています。また、学振は特別研究員制度を設け、博士課程在籍者やポストドクターに対して奨励費を提供し、若手研究者の育成を図っています。 これらの取り組みにより、学振は研究者が必要とする資金を提供し、学術研究の発展に寄与しています。個人が資金を得る代表的な手段でもあります。
学振の特別研究員に採用されると、以下の支援を受けることができます。
- 研究奨励金 (特別研究員-PD(博士の学位取得者)の場合)
- 金額:月額362,000円(予定額)
- 用途:自由に使用可能で、使用報告の義務はありません。
- 科学研究費助成事業(科研費)
- 特別研究員奨励費:自身の研究に必要な費用として、年間最大150万円を申請可能です。
- 用途:研究活動に限定され、基本的に支給された金額は1年間で使い切る必要があります。
これらの支援により、特別研究員は研究に専念しやすい環境が整えられています。
NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)とは?
NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)は、産業技術やエネルギー分野の研究開発プロジェクトを支援し、競争的資金を通じて研究開発の促進を図る国立研究開発法人です。イノベーションの創出を目的として設立され、持続可能な社会の実現に向けて革新的な技術の研究開発や実証を推進しています。特に、エネルギーや環境問題、産業技術などの分野でリスクの高いプロジェクトに挑む「イノベーション・アクセラレーター」としての役割を果たしています。
NEDOから研究開発費の獲得を検討する際のポイントは?
NEDOから研究開発費の獲得を検討する際は、以下のポイントを抑えておくと効果的です。
(1)公募分野の理解と戦略的なテーマ選定
NEDOはエネルギー、環境、産業技術分野を中心に公募テーマを設定しています。自社・自組織の研究開発計画がこれらの重点分野に合致しているかを確認し、NEDOが掲げる政策的目標や技術戦略と整合性のあるテーマを選ぶことが重要です。
(2)実用化・社会実装志向の明確化
NEDOは研究開発成果の実用化や社会実装、さらには市場創出までを視野に入れたプロジェクトを重視します。単なる基礎研究ではなく、事業化・商用化までのロードマップや、社会的インパクト、ビジネスモデルを明確に示すことで採択率向上が期待できます。
(3)技術的リスクと挑戦性の評価
「イノベーション・アクセラレーター」として、NEDOはリスクの高い先進的・革新的技術開発に資金を投じる傾向があります。提案する技術の新規性や独自性、既存技術との差別化要因、技術的ハードルの明確化とその克服戦略が重視されます。
(4)産学官連携・チームビルディング
大規模・先端的なプロジェクトほど、大学や研究機関、他社との協業・コンソーシアム形成が期待されます。多様なステークホルダーとの連携によるシナジー創出や、研究開発から実証・事業化までをカバーする総合力が求められます。
(5)明確な予算計画・管理体制
公的資金を扱うため、研究計画書には詳細な経費見積りや資金使途の明確化、適切なマネジメント体制が必須となります。採択後も厳正な報告・審査が行われるため、透明性の高い管理体制を構築しておくことが重要です。
(6)成果評価とフィードバックループの構築
NEDOは中間評価や最終評価を行い、進捗や達成度を厳密にチェックします。評価結果をプロジェクト計画にフィードバックし、柔軟に戦略や手法を修正できる体制を整えることで、プロジェクト成功率が向上します。
これらを踏まえて、NEDOの公募要領や評価基準を十分に読み込み、自社が目指す技術開発の方向性と適合させることで、採択可能性を高めることができます。
JST(科学技術振興機構)とは?
JST(Japan Science and Technology Agency)は、科学技術とイノベーション政策を推進する国立研究開発法人です。その目的は、科学技術を通じて社会の課題解決やイノベーションの創出を支援し、安全で豊かな社会を実現することです。主な活動には以下があります。
- 研究開発の支援: 戦略的研究プロジェクトの資金提供と運営。
- シンクタンク機能: 科学技術政策に関する調査、分析、戦略提案。
- コミュニケーション: 科学技術の社会的理解を深める活動。
- 環境整備: 科学技術の発展を継続的に支える仕組みづくり。
主要なファンディングプログラム
JSTは、大学や研究機関、企業などの研究者に向けて、多様なファンディングプログラムを提供しています。主なプログラムは以下の通りです。
(1)戦略的創造研究推進事業
-
- CREST: チーム型で挑むネットワーク研究。研究期間5.5年、研究費は1.5億~5億円。
- さきがけ: 若手研究者の個人型研究支援。研究期間3.5年、研究費は3,000万~4,000万円。
- ERATO: 卓越したリーダーによるプロジェクト型研究。研究期間5.5年、総額12億円。
(2)大学発スタートアップ支援
-
- A-STEP: 大学の研究成果を企業に技術移転する支援。年間上限2,500万円。
- START: 起業準備段階の研究者への支援。年間上限3,000万円、期間2.5年。
- SUCCESS: JSTの成果を活用するスタートアップへの最大5億円の出資。
(3)未来社会創造事業
-
- 革新的技術の開発を支援する大規模プロジェクト型研究。最大10年間で27億円までの資金提供。
(4)グローバル研究連携
-
- SATREPS: 地球規模課題に対応するODA連携プログラム。
- ASPIRE: 国際頭脳循環を促進するプログラム。
(5)若手研究者育成
-
- BOOST: 次世代AI分野の博士学生や若手研究者への支援。
-
- FOREST: 自由で挑戦的な研究を長期的に支援。
(6)GX(グリーントランスフォーメーション)推進
-
- GteX: 蓄電池や水素、バイオものづくり技術の研究開発を推進。最大5年間で30億円。
GAPファンドの概要と役割
GAPファンドは、大学の基礎研究から事業化に至る過程で生じる「資金の空白」を埋めるために提供される助成金です。このファンドの目的は、研究成果を市場に出すための実証や技術実用化を支援することで、特にスタートアップ創業前の研究者にとって重要な資金源となっています。
GAPファンドの効果
- 技術移転の成功: GAPファンドによって研究成果の事業化が進むと、大学はライセンス収入を増やし、その収益を新たな研究に再投資できます。
- 知的創造サイクルの形成: 再投資によって大学内の研究活動が活性化し、次世代の事業化が促進されます。
日本におけるGAPファンドの支援制度
GAPファンドは、大学などの研究機関で生まれた基礎研究成果を事業化する際に生じる「資金の空白(ギャップ)」を埋めるための支援制度です。このファンドは、研究成果の実用化や市場投入を目指す際に必要となる資金やサポートを提供し、技術シーズの事業化を促進します。
日本においては、科学技術振興機構(JST)が主導する「大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム」などが代表的なGAPファンド支援制度として知られています。このプログラムでは、大学や研究機関の技術シーズを発掘し、研究開発費の提供や起業ノウハウの提供、ビジネスモデルのブラッシュアップ、メンタリングなど、事業化に向けた総合的な支援を行っています。
また、各大学でも独自のGAPファンドプログラムを設け、研究者や学生の起業や事業化を支援しています。例えば、京都大学の「ダイキンGAPファンドプログラム」や、大阪大学の「ベンチャー創成・社会実装支援」などがあり、これらのプログラムを通じて、研究成果の社会実装が進められています。
GAPファンドの活用により、研究者は自身の研究成果を事業化するための資金やサポートを得ることができ、大学はライセンス収入の増加や新たな研究開発への再投資を通じて、知的創造サイクルを形成することが期待されています。
JSTが提供する「大学発新産業創出基金」は、以下の2つの資金流れで構成されています。
- 拠点地域プラットフォーム経由
- STEP1: 単年500万円程度の小規模支援。
- STEP2: 複数年で6,000万円~1億円規模の大型支援(VCなどの事業化推進機関との共同申請が必要)。
- 研究者への直接支援
- 「D-Global」プログラムでは、3年で最大3億円(場合によっては5億円)の大型資金が提供されます。
GAPファンドは、研究者が技術の事業化に向けて新たな一歩を踏み出すための重要な支援ツールとして創業前の研究者にとって貴重なリソースとなっています。
その他の研究資金について
日本の研究者が利用できる競争的資金は、多岐にわたります。以下に主なものを挙げます。
- 科学研究費助成事業(科研費):文部科学省と日本学術振興会(JSPS)が提供する、日本最大規模の競争的研究資金です。基礎から応用まで幅広い研究分野を対象としており、研究者個人やグループが申請可能です。(科研費は助成金であると同時に、競争的研究資金の一種です。助成金の中でも「研究者の競争」を前提とした仕組みを持つため、一般的な助成金とは異なる特性を持っています。このため、科研費を説明する際には「競争的研究資金」として紹介されることが多いです。)
- 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP):内閣府が主導するプログラムで、基礎研究から社会実装までを一貫して推進します。産学官連携による分野横断的な研究開発を支援しています。
- 研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム(BRIDGE):内閣府が実施するプログラムで、革新技術の社会実装や新事業創出を目指し、各省庁の施策を連携・加速させることを目的としています。
- 日本医療研究開発機構(AMED)の競争的研究費:医療分野の研究開発を支援するため、AMEDは多様な競争的研究費プログラムを提供しています。
- 農林水産省の競争的研究資金:農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)などが提供する、農林水産業に関連する研究開発を支援する資金です。
- 環境省の競争的研究資金:環境問題に関する研究を支援するための競争的資金が提供されています。
地方自治体
地域独自の競争的資金プログラムを提供している場合があります。
-
- 地域の大学や研究機関、企業を対象とした助成金。
- 例:都道府県が提供する「地方創生関連研究助成」など。
民間財団
民間財団において、研究費を得ることができます。代表的な財団をご紹介します。
- トヨタ財団
- 国際的な共同研究や環境保全をテーマにした助成金。
- 住友財団
- 人文科学や自然科学分野の研究助成。
- 三菱財団
- 医学や自然科学、社会科学に特化した研究費。
- アカデミスト(academist)
- 学術研究のクラウドファンディング。
国際的資金
日本からも国際的な研究資金プログラムに応募することができます。代表的なものをご紹介します。
- Horizon Europe(EU)
- 日本の研究者も応募可能なEUの競争的研究資金プログラム。
- NIH(米国国立衛生研究所)
- 医療・生物学系研究者を対象とした助成金。
申請書をより良くするコツ

4-1. 読み手(審査員)の目線を想像する
審査員は限られた時間で多くの申請書を読みます。研究の重要性や新しさが、一目で伝わるような書き方を意識しましょう。専門用語ばかり並べず、背景や目的を分かりやすく説明することが大切です。
4-2. 成果の見通しを具体的にする
「こうなったらいいな」という抽象的な表現よりも、「この研究で得たデータをもとに、○年以内に論文発表を目指す」「この成果は将来この分野の理論を塗り替える可能性がある」といった具体的なビジョンが求められます。目標がはっきりしていると、資金を出す側も納得しやすくなります。
4-3. 予算の使い方を明確にする
助成金は大切なお金です。「この実験装置を買う」「フィールド調査のための交通費に充てる」など、使い道をはっきりさせ、無駄遣いしないことを示しましょう。現実的で納得できる予算計画は、信頼性を高めます。
4-4. 周囲からのフィードバック
自分一人で書いていると、気づかない欠点が多いものです。同僚や上司、研究支援部署の人などに申請書を読んでもらい、アドバイスをもらうことで、文章や内容をブラッシュアップできます。
資金獲得後も大切なこと

5-1. 進捗報告や成果発表
助成金を受け取ったら、定期的に進捗報告や最終報告を行います。これは資金提供者への義務であり、資金が有効に使われていることを示す大事な機会です。また、研究成果は論文や学会発表を通じて世の中に発信しましょう。それが次の資金獲得や評価にもつながります。
5-2. 次のステップへの準備
一度資金を獲得して研究を進めている間にも、次の助成金申請や他の資金源の情報収集を行い、継続的な研究の土台を築くことが大事です。今回の成果をもとに、より大規模な助成金や新たな共同研究先を探せば、研究の幅が広がります。
5-3. 産学連携や社会へのアピール
もし研究成果が実用的なものであれば、企業や自治体との連携が進む場合もあります。そうすれば、新たな研究資金やプロジェクトにつながりやすくなります。また、研究内容や成果をわかりやすく一般向けに発信することで、社会的な支持を得て、新たな寄付やファンディングチャンスが生まれるかもしれません。
最近の動きや新しい流れ

6-1. クラウドファンディングの発展
インターネット上で一般の人たちから広く資金を募るクラウドファンディングは、研究分野でも活用が広がっています。これは研究内容をわかりやすく伝えて、多くの人に「この研究を応援したい」と思ってもらう必要があるため、研究者にはコミュニケーション能力も求められます。
6-2. 社会課題解決型の助成増加
地球温暖化、感染症対策、エネルギー問題、少子高齢化など、社会や地球規模での課題が目立つようになる中、その解決に貢献する研究を支援する助成制度も増えています。社会的インパクトのある研究テーマは、今後ますます注目されるでしょう。
6-3. 若手研究者支援の拡充
日本を含む多くの国で、若手研究者の育成が重要課題となっています。そのため、若手を対象とした助成制度や、ポスト(職位)の整備、海外留学支援などが充実してきています。若手にとっては、これらの制度を上手く活用してキャリアを軌道に乗せるチャンスです。
6-4. 国際共同研究や学際的な研究への注目
一つの分野だけでなく、複数の異なる分野が手を組んで新しい知見を創り出す「学際研究」、また複数の国の研究者が協力して行う「国際共同研究」などが重視されるようになっています。こうした取り組みには特別な資金枠が用意されていることもあり、グローバルなネットワークづくりが資金獲得につながる場合があります。
まとめ

研究者が資金を得る方法は年々多様化しています。国の助成金、海外の助成制度、企業との契約、財団の支援、クラウドファンディングなど、選択肢はたくさんあります。どの方法にも、申請書や企画書をしっかり作り、わかりやすくアピールする努力が求められます。
研究資金を得る過程は、ただお金を手に入れるだけでなく、研究の目的や手法を明確にし、自分の研究を客観的に捉え直すよい機会でもあります。また、資金を得た後は計画通りに研究を進め、成果をわかりやすく発信し、次の資金確保や新たなパートナーシップを目指していくことが重要です。
研究資金の確保は簡単なことではありませんが、時代の流れや支援制度を理解し、自分なりの戦略を練り上げることで、チャンスは広がります。研究者としてのキャリアを築く上で、資金獲得力は欠かせないスキルとなっています。困難も多いですが、新たな知識や発見を生み出すためのプロセスとして、前向きに取り組んでいただければと思います。
※参考文献
事業の概要 | 戦略的創造研究推進事業
ファンディングを利用したい・利用中の方
未来社会創造事業
ファンディングを利用したい・利用中の方
BOOST|JST
創発的研究支援事業|JST
ファンディングを利用したい・利用中の方
2024年度 JST概要パンフレット
文部科学省の競争的研究費一覧
令和6年度競争的研究費制度一覧(制度概要)
AMEDの競争的研究費一覧
2024年度 研究助成プログラム
住友財団
助成について-自然科学研究助成:公益財団法人 三菱財団
academist (アカデミスト)
共同開発がしたいです | EU-Japan
厚生労働省eJIM | NIH RePORTERでNIHからの資金提供による研究についての情報を探す